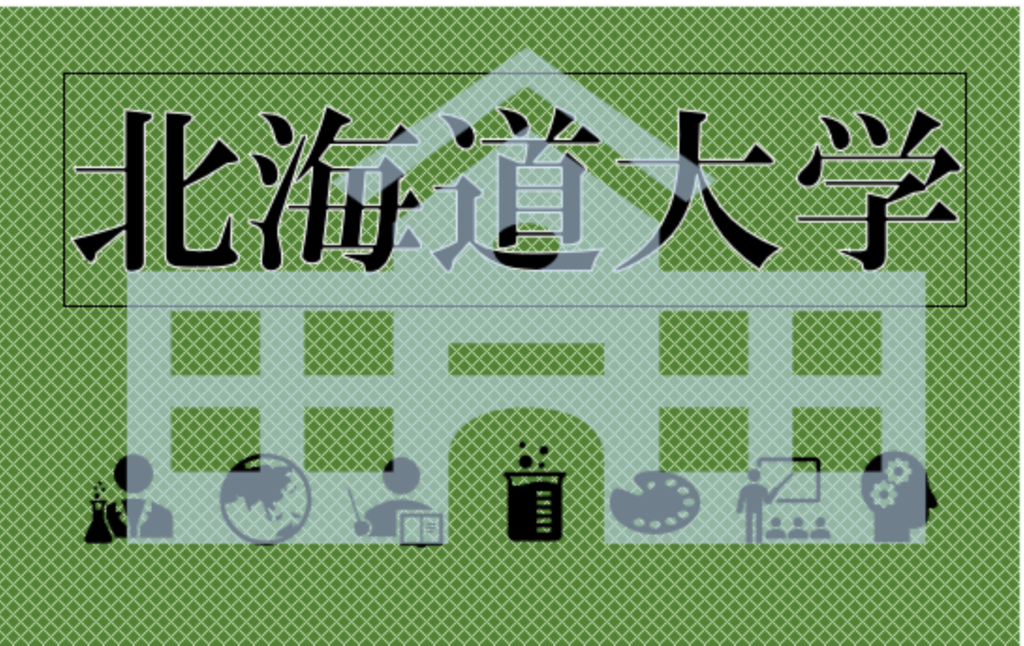北海道大学サステイナビリティ推進機構は、札幌市、上川郡下川町、法政大学及び関西大学と連携し、9月3日及び同10日〜12日にかけて、官学連携による「カーボンニュートラル夏季短期学習プログラム」を実施した。北大をはじめ、法政大学及び関西大学から計27名の学生が参加し、カーボンニュートラル(CN)に関する理論と実践を学ぶ貴重な機会となった。

同プログラムは、カーボンニュートラルに関する知識の習得と、地域特性を踏まえたエネルギー政策への理解促進を目的とするもの。講義、フィールドワーク、グループワーク及びグループ発表を通じて、参加者に実践的な学びの場を提供した。
事前学習として、参加者はカーボンニュートラルの基礎学習動画を視聴し、「自分が住んでいる地域(地元も可)」または「自ら選定した任意の地域」におけるカーボンニュートラルの取組について調査し、レポートを提出する課題に取り組んだ。
9月3日にはオンライン形式で事前学習が行われ、『地域ごとのエネルギー戦略・カーボンニュートラルの取り組み紹介』と題して、株式会社まち未来製作所及び公益財団法人地球環境産業技術研究機構による講義が行われた。
10日から12日にかけては、札幌市内で対面形式のプログラムを実施した。初日には、札幌市及び下川町の職員による自治体における脱炭素の取組に関する講義を行い、参加者は自治体の特性に応じた施策について理解を深めた。講義後には交流会も開催し、参加した学生にとって他大学の学生との交流を深める機会となった。
11日には、参加した学生が、札幌市の脱炭素の取組を現地で学ぶため、北海道ガス㈱新さっぽろエネルギーセンター、同社本社及び㈱北海道熱供給公社の施設を訪問した。そのなかで、学生は、積雪寒冷地である札幌市では熱需要が高く、コージェネレーションによって電力・ガス・排熱を効率的に活用する取組が行われていることや、札幌市及び近郊からの建設廃材や林地未利用材を活用した木質バイオマスの取組についても学習。地域資源を活かした脱炭素技術の実例に触れることができた。

最終日の12日には、『日本の自治体単位で2050年カーボンニュートラルを達成する方法』をテーマに、六つのグループに分かれてグループワークを実施。学生たちはグループごとに自治体を想定し、現状とあるべき姿を抽出したうえでギャップ分析(As-is/To-be分析)(※1)を行い、対策手法をKJ法(※2)で整理し、ペイオフマトリクス分析(※3)により解決策を導出した。
最後に、これらの成果をプレゼンシートにまとめ、グループ発表を実施した。参加した学生とって、地域特性によってあるべき姿や課題が異なることを実感し、カーボンニュートラル達成に向けた解決策も一様ではないことを理解するとともに、地域課題の解決に向けた実践的な手法を習得する機会となった。
※1:現状と理想の状態との間に存在する「ギャップ(隔たり)」を特定し、そのギャップを解消するための戦略を立てる分析手法のこと。
※2:付箋などの紙に自分の思いついたアイデアを書いていき、それをグループ化していくことで、脳内で思いついたアイデアを言語化していく手法のこと。
※3:複数の要望や意見に対して、一定の基準をもとに優先順位をつける基本のフレームワークのこと。