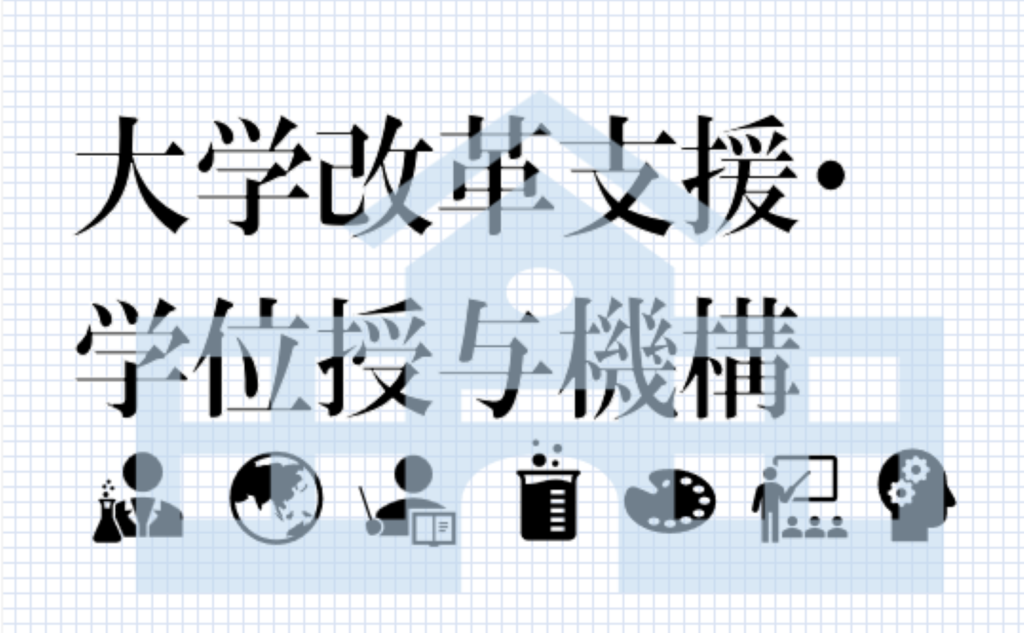(本文)
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、「キャンパス・アジア(CAMPUS Asia※1)」発足当時より、中国教育部教育質評価センター (Education Quality Evaluation Agency of the Ministry of Education:EQEA)※2及び韓国大学教育協議会(Korean Council for University Education:KCUE)と連携しながら、日中韓の大学間交流を質保証の側面から支援する取組を行っている。
※1 Collective Action for Mobility Program of University Students in Asiaの略
※2キャンパス・アジア発足当時は、中国教育部高等教育教学評価センター(Higher Education Evaluation Center of the Ministry of Education:HEEC)
「キャンパス・アジア」は、質の保証を伴った学生交流を推進するため、日本・中国・韓国の政府により立ち上げられた構想。2009年の第2回日中韓サミットにおいて、3か国間で質の高い大学間交流を行うことが提言されたことを機に、2010年4月に同3か国の政府・大学・産業界関係者による日中韓大学間交流・連携推進会議が発足し、「キャンパス・アジア」の取組が開始した。アジアにおける大学間交流の推進を通して、グローバル人材の育成と大学教育のグローバル展開力の強化を目指すとともに、プログラムやカリキュラムの質の保証にも重点が置かれている。
「キャンパス・アジア」は5年間を1モードとし、第1モード(2011~2016年度:試行期間)、第2モード(2016~2021年度:本格実施)を経て、2021年度より第3モード(2021~2025年度:参加国の拡大)が始まった。第1モード、第2モードでは、同機構はEQEA及びKCUEと連携して「キャンパス・アジア」採択プログラムのモニタリングや優良事例の取りまとめを行った。
2019年9月に開催された第7回日中韓大学間交流・連携推進会議で、日本は、日中韓以外のアジア各国・地域からの参画を得て、アジア全域で質の保証を伴った大学・学生間交流を活発化するための理念を提唱した。これを踏まえ、第3モードでは、大学・学生間交流プログラムの参加対象国が日中韓3か国の枠を越え、更に発展・拡大することを目指し、3か国の質保証機関の協力のもとで共通の質保証基準を策定することが合意された。
共通質保証基準は、①キャンパス・アジアの拡大と、②キャンパス・アジアが発足当初から理念として掲げる「質の保証を伴った」交流―という2つの軸に貢献していくため、アジアでの学生交流プログラムに望まれる質についての共通認識を図り、大学側の持続的な質保証活動を支えるための共通の参照点となることを意図した基準。
基準の策定に向けた作業は、大学・学生間交流プログラムの海外事例や留意すべき質をまとめたガイドライン・参照文書等の先行事例調査から始まり、その後、基準(素案)に関するオンライン・アンケート、基準(案)に基づく聞き取り調査、日中韓及びASEAN諸国等の有識者への意見聴取等の実施により、大学コンソーシアム関係者や有識者から様々な意見を聴取した。これらの調査等で示された助言や提案をもとに、日中韓の質保証機関で基準案の推敲を重ね、今年4月に共通質保証基準が確定した。
アジアではさまざまな交流形態のプログラムが展開され、規模も拡大するなか、社会情勢の変化等による不確実性の高い時代でも、プログラムの一層の構築・機能促進と自律的・持続的な質保証・向上の取組を支援するという観点から、「多様性の考慮」、「柔軟性の促進」、「持続的な質保証支援」の3つを基準における不可欠な要素として整理し、基準の道筋を定めた。完成した基準は、4つの基本原則と以下の8つの基準で構成されている。
1.目的設定と共有
2.実施体制
3.カリキュラム
4.学生の受入・派遣
5.学習・生活支援
6.学習成果
7.単位互換・学位の授与
8.継続的な質の向上
共通質保証基準の詳細は同機構の「キャンパス・アジア‐共通質保証プロジェクト‐」ウェブサイトに掲載されている。(https://qacampusasia.niad.ac.jp/common-quality/common-quality-assurance-standards.html)