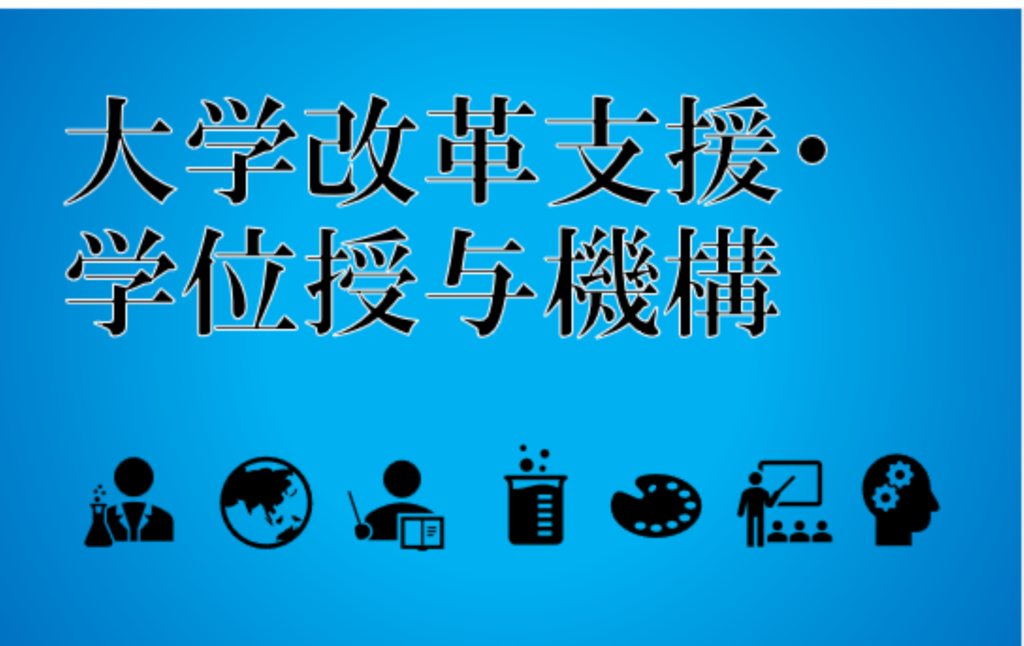大学改革支援・学位授与機構は、令和6年度大学質保証フォーラムをこのほど開催した。今回は『質保証の地殻変動―英国の最新動向から学ぶ』をテーマに実施。英国高等教育質保証機構(QAA)機構長のヴィッキー・ストット氏から、近年の英国の高等教育質保証制度の大きな変化と、本質的意味について話を聞くとともに、日本の高等教育機関質保証の将来像を模索するために議論した。

当日の進行を同機構の森利枝・研究開発部教授が務め、プログラム前半では服部泰直機構長の開会挨拶に続き、ストット氏による基調講演が行われた。
ストット氏は、英国の高等教育質保証のモデルは、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドそれぞれで違い、QAAの業務範囲も各地域のセクターのニーズによって異なっていることを紹介。さらに、ここ数年の傾向として、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドでは質保証と規制の全体的な方針の整合性が増しつつある一方、イングランドのアプローチは異なる方向に進んでいることが述べられた。

特にイングランドでは、登録審査の一部を受託していた高等教育機関登録制度からの撤退によるQAAの役割の変化として、機関登録制度が質のベースライン(最低要件)の充足を重視している。一方、QAAはベースラインを超えた高等教育の質を実現するために、会員校向けに助言やガイダンス、グッド・プラクティスの提供といった支援を行うなど、高等教育の環境の変化に対応した多用途で柔軟な活動ができるようになったことが強調された。
また、人工知能(AI)の進展による高等教育への影響を踏まえ、QAAは機動的に関連情報を提供しており、将来AIの存在が当たり前となった社会に高等教育がどのように適合するかを考え、アカデミック・スタンダードを確保し、学生の学習体験を向上させるようなAIの活用に重点を置きたいとの意見も述べられた。
プログラム後半の質疑応答・ディスカッションでは、同機構の戸田山和久研究開発部長がモデレーターを務め、参加者との質疑応答を交えながら、テーマを巡る議論が展開された。参加者からは、QAAの質保証活動への学生の参画や、レビューパネルへの産業界や外国からの登用の状況、評価におけるグッド・プラクティスの抽出方法についての質疑応答があった。

また、QAAが撤退した高等教育機関登録制度の実施主体である学生局(OfS)については参加者の関心も高く、役割についてQAAとの比較を交えながら回答があった。さらに、大学の自治の担保や大学が認証評価を受ける意義といった話題にも及び、活発な意見交換が行われた。最後に同機構の光石衛理事の閉会挨拶により、大いに盛り上がったフォーラムは幕を閉じた。
今年度はオンライン・会場のハイブリッド形式で開催し、高等教育機関関係者を中心に国内外から約370名が参加した。フォーラムの講演資料は同機構のウェブサイト(https://www.niad.ac.jp/consolidation/international/forum/)に掲載している。