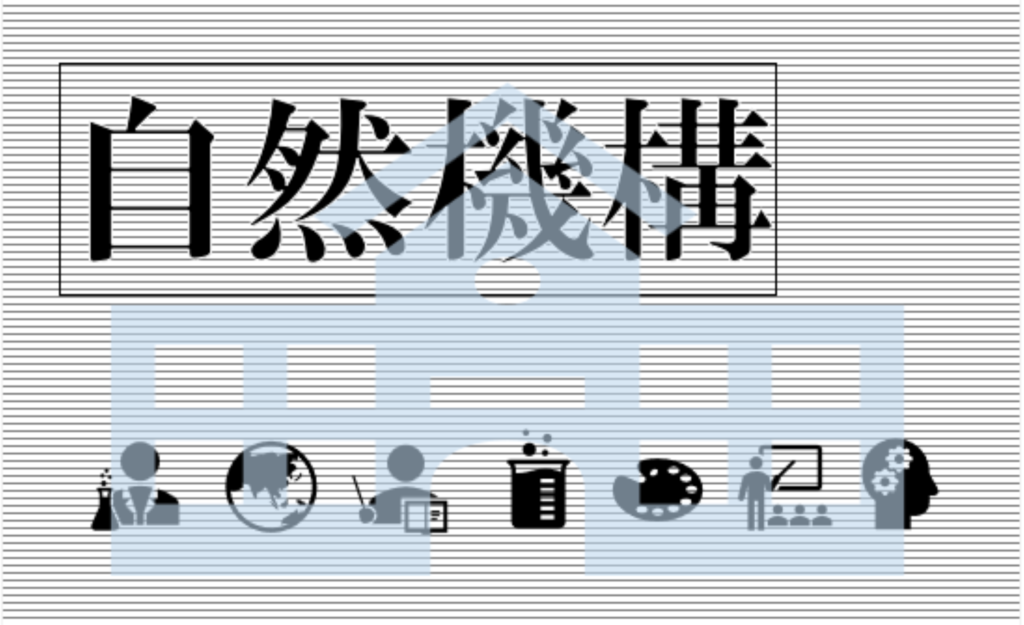自然科学研究機構基礎生物学研究所の金井雅武特任助教らを中心とする共同研究グループは、モデル植物「シロイヌナズナ」を用いて種子貯蔵たんぱく質の遺伝子の末端に、大量蓄積するために不可欠な配列が存在することを明らかにしたと発表した。
特定のたんぱく質だけを大量に蓄積する特徴を持つ植物種子は、次世代のたんぱく質工場としての期待が高まっている。だが、種子がどのようにして特定のたんぱく質だけを大量に蓄積しているのかは不明であった。
研究では、シロイヌナズナの種子貯蔵たんぱく質である12S1たんぱく質をコードする12S1遺伝子から蓄積に必要な領域を探索したところ、遺伝子の末端に存在する非翻訳領域(3‘UTR)が種子における大量蓄積に必要不可欠であると見いだした。
この3‘UTRが他の遺伝子でも機能するかどうかを検証するため、通常であれば種子に蓄積しないたんぱく質である、リンゴ酸脱水素酵素(pMDH1)をコードする遺伝子の末端にこの3’UTRを付加したところ、リンゴ酸脱水素酵素を大量に蓄積させることを確認した。
さらにバイオ医薬品であるインターフェロンの1つであり、人間のC型肝炎ウイルスの治療薬候補であるインターロイキン28B(IL28B)をコードする遺伝子の末端に12S1遺伝子の3‘UTRを付加しシロイヌナズナに導入することで、シロイヌナズナ種子にインターロイキン28Bを大量に蓄積させることに成功した。
研究グループは、「今後は、3‘UTRの働きをさらに詳細に解明することで、バイオ医薬品や工業用酵素を植物種子で作ることが可能となる」とコメントしている。