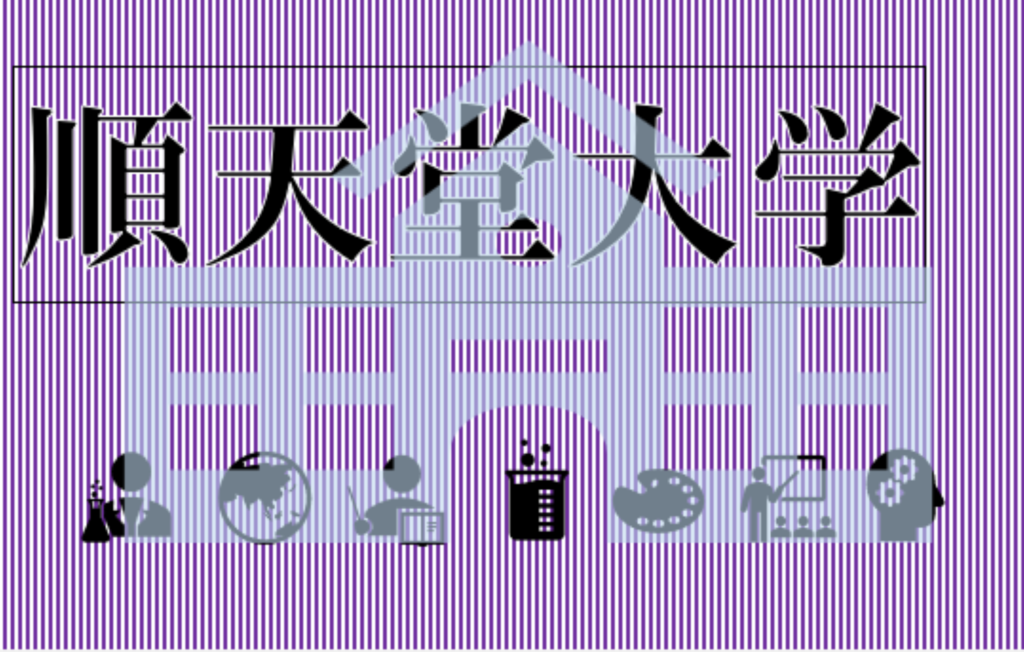順天堂大学と東レの共同研究チームは、がんの治療に用いられる分子標的型抗がん剤の副作用である皮膚障害の発症機序の一端を解明し、それを抑制する薬剤を4種類発見した。既存の外用薬によりがん治療中の患者の生活の質が向上することが期待されている。
分子標的型抗がん剤は脱毛や骨髄抑制、吐き気などの副作用が少ない一方で、ニキビや炎症といった症状が生じやすい。だが、その発症プロセスは分かっておらず、治療法は対症療法しかなかった。
研究グループは分子標的型抗がん剤の一種「ソラフェニブ」による手足症候群に注目。そのメカニズムの解明と新規治療法を開発することを目的に、スクリーニングを行い細胞保護剤の探索とその作用機序の解明を行った。
研究では約1200種の既存医薬品から構成されるライブラリーを用いて、ソラフェニブによる表皮の細胞毒性を軽減する薬剤を調査した。その結果、「クロファジミン」、「シクロスポリンA」、「イトラコナゾール」、「ピルビニウムパモ酸塩」が抗がん剤の毒性を抑えると判明した。
その機序を探っていくと、これらの薬はソラフェニブによる「ERK1/2」のリン酸化阻害を解除し、アポトーシスを抑制、細胞増殖を正常化することで表皮角化細胞に対する細胞保護作用を発揮していると考察されている。
研究チームは「候補薬は共通してアポトーシス阻害作用を示したが、細胞増殖促進作用やERK1/2リン酸化の正常化作用は候補薬により、違いがあったため、個々の候補薬の細胞保護メカニズムに関しても解析を進めていく」と力を込めた。