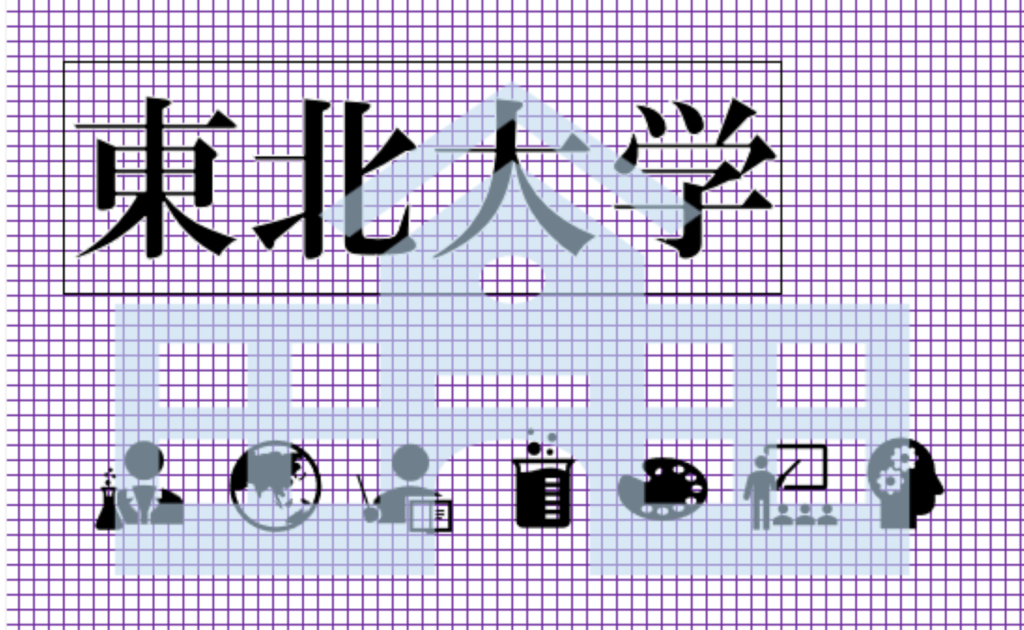災害など緊急の際に情報を外国人に迅速に伝達し安全を確保するために、外国人日本語学習者が迅速に単語を理解できる要因の解明が求められている。東北大学大学院文学研究科の趙雪含大学院生、同木山幸子准教授、成蹊大学文学部の熊可欣准教授(研究当時:学際科学フロンティア研究所助教)は、中国人上級日本語学習者を対象とした実験を通じて、漢字圏出身者にとっては「漢字を減らす」方針が、むしろ迅速な理解の妨げとなることを例証した。
研究グループの実験の結果、母語で漢字を使う中国人は、日本語を理解する際にも漢字に強く依存し、「ごみ」など平仮名で書かれた和語より「硬貨」など漢字で書かれた漢語の方が速く理解できた。和語でも「紙くず」など漢字が含まれていれば速く理解できた。
この知見は、外国語の読解の効率性は、読み手の母語に よって異なることを具体的に実証するもので、外国人向けの行政や教育等の案内でも、読み手の母語に応じて表記を調整する必要があることを示唆している。この研究成果は、10月23日に国際学術誌International Journal of Applied Linguisticsに掲載された。
現在日本には360万人近くの外国人が暮らしており、特に災害や行政に関する重要な公共情報の伝達で、効果的な方法を確立する必要度は増す一方。文化庁・出入国在留管理庁が公表した外国人向けの日本語発信のガイドラインである「やさしい日本語」は、全国の各自治体で活用が拡大しているが、どのような日本語の表記法が理解しやすいかは、外国人の中でも決して同じではない。
人は未知の言語を学ぶ際、既知の言語との共通点を手がかりとしながら、脳内に心内辞書を形成していくことが知られている。日本に在住する外国人には漢字文化圏出身者が多くいるが、特に第1位の中国語を母語 (first language:L1)として日本語を学ぶ者(中国人日本語学習者)にとっては、第二言語(second language:L2)の日本語を学習する時には、 形態音節文字である「漢字」という共通資源が意味を理解する強い手がかりとなり、非漢字圏出身者に比べて圧倒的に有利。
しかし、日本語の漢字は中国語とは異なり複数の読み方があり、大きく分けて中国語由来の漢語の音読みと、日本語由来の和語の訓読みが存在する。また、日本語は漢字だけでなく、音節文字である仮名も使う。
こうした日本語の語彙体系や表記法の複雑さにより、中国人日本語学習者が必ずしもL2である日本語の語彙理解において有利とばかりはいえない可能性がある。災害など緊急の際に迅速に正確な情報を伝達し、外国人の安全を確保するためにも、外国人の日本語学習者が迅速に理解できる単語とそうでない単語がどのように決まるのかを明らかにする必要があった。