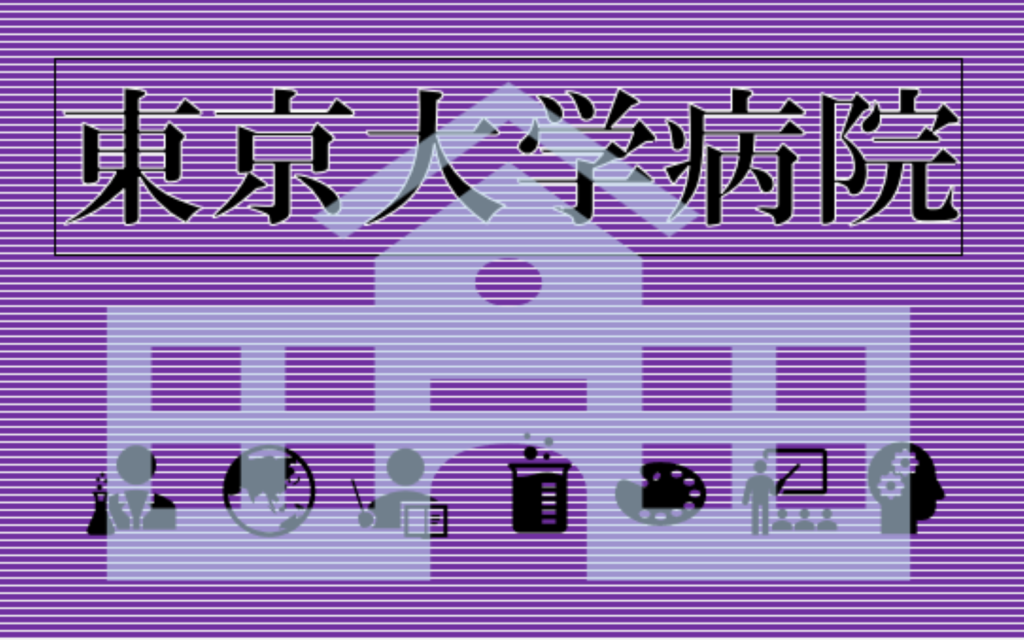約6割が副作用の懸念や投与頻度の多さを理由に治療薬投与に至らなかった症例の経験があると回答。四分の一の医師はベッドや人員のひっ迫を感じている-。
◇ ◇
アルツハイマー病に対する疾患修飾薬としてレカネマブ、ドナネマブといった新薬(抗アミロイド抗体薬)が登場し、2023年12月からレカネマブは国内で臨床実用されている。抗アミロイド抗体薬の安全・適正な使用のためには多くの事前検査を行なった上で、投与にあたって各種要件を満たした施設・医師によって投与されることが重要。しかしこのような条件を満たす施設・医師、また治療枠の数は必ずしも十分ではないため、各医療機関で必要な患者へ検査や治療が十分に提供できない可能性、また地域ごとの格差がある可能性なども懸念されていた。
こうした現状を踏まえて、東京大学大学院医学系研究科認知症共生社会創成治療学の岩坪威特任教授、筑波大学附属病院の新井哲明教授らのグループは、厚生労働省の令和6年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「認知症医療の進展に伴う社会的課題への対応のための研究」(代表:新井哲明)」の一環として、抗アミロイド抗体薬を処方可能な認知症関連の専門医を対象に、昨年12月から今年1月にウェブアンケート調査を実施し、使用状況、副作用の出現状況など新薬診療の最初の1年間の実態、また治療上の課題などについて調査を行った。
岩坪特任教授らは、アルツハイマー病治療薬実用化1年時点(アンケートを実施した 2025年1月の時点)で、全国の認知症関連専門医を対象にウェブアンケート調査を実施し、レカネマブ投与経験のある専門医311名の回答を集計した。
調査によると、初診から初回点滴までの待機期間は、約8割が「3か月以内」と回答し、一定のアクセスが確保されている傾向が示された。また、安全面では、特異的な副作用(ARIA)による治療中止症例を経験したことがある専門医は非常に少なく、実臨床での安全性はおおむね良好と認識されていると考えられるという。
一方で、外来点滴スペースや人員体制等治療提供の運用上の課題、さらに一部検査運用に関する課題が挙げられた。
この研究によって今後のアルツハイマー病新薬治療のより安全・適正・持続可能な提供への施策のための基礎的資料となることが期待できる。
□調査結果詳細
《初期アクセスと安全性》
◎回答者の約8割が「初診から最初の点滴投与までの待機期間は平均的に3ヶ月以内」と回答し、比較的スムーズであることが示された。
◎副作用による治療中止を経験したことがある専門医の割合は限定的で、また6〜7割の医師が副作用の発生頻度は臨床試験のデータよりも低い印象を持っていると回答しており、実臨床における安全性プロファイルは比較的良好であると認識されていると考えられる。
◎回答者の約6割が副作用の懸念や投与頻度の多さを理由に治療薬投与に至らなかった症例の経験があると回答しており、治療薬投与に際しての負担の軽減に資する運用上の工夫の必要性が考えられる。
《治療・検査運用上の課題》
◎治療インフラの課題:約4分の1の医師が「点滴のための外来スペース(ベッド)や人員が逼迫している、または枯渇している」と回答。また、6割以上が「自施設の治療提供能力は、想定される患者需要に満たない」と感じており、今後の患者増に対応できない懸念があると考えられた(病院の治療キャパシティの課題)。
◎検査運用・薬剤投与上の課題:診断・説明・リスク評価に資する一部検査の運用に関するハードルなどを約半数の医師が課題と認識しており、(治療未経験の医師に比べて)治療経験のある医師により強い課題意識がみられた。
◎また治療の実施、継続のためには医療機関間の連携(初回導入施設から継続投与施設へのスムーズな紹介など)や、アルツハイマー病や抗アミロイドβ抗体薬に関する普及・啓発が一つの鍵になると考えられるが、これらの点が課題であるという回答が特に治療経験のある医師から示された。