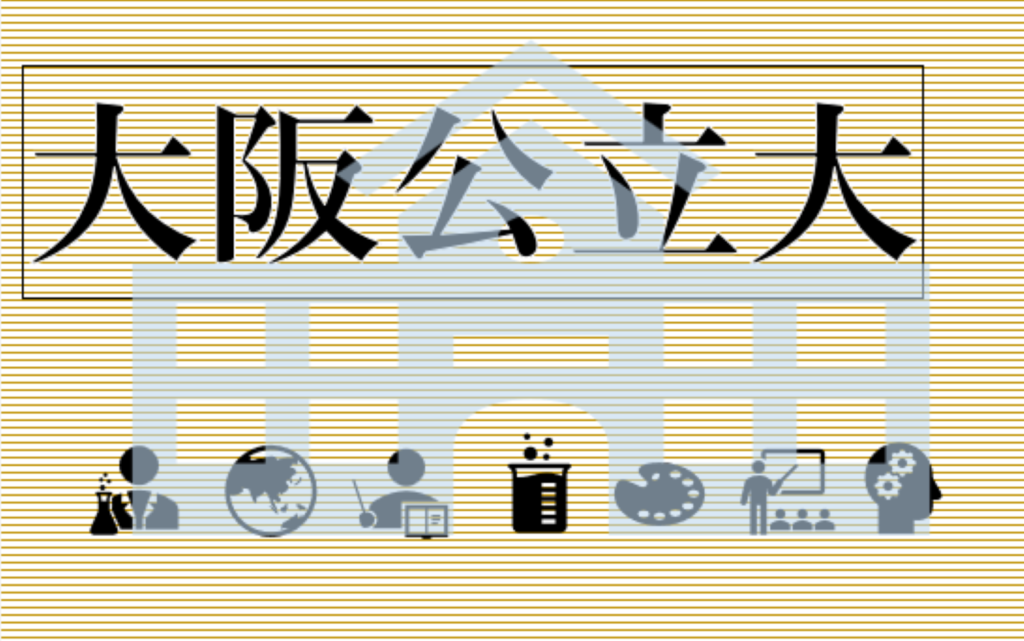大阪公立大学大学院生活科学研究科の松下大輔教授らの研究グループは、昨年9月に 東京都区部(東京23区)に通勤する40歳~59歳の首都圏在住者を対象に、通勤時間と住宅 面積が不眠症と日中の眠気にどのような関係があるかについてオンライン調査を実施し、 1757人分の回答を分析した。その結果、長い通勤時間は不眠症と日中の眠気を引き起こす要因になり、小さい住宅面積は不眠症を引き起こす要因になることが判明した。
また、4人世帯用住宅面積(95㎡)の規模で通勤時間が52分を超えると、不眠症リスクが高くなることがわかった。
この研究結果は、住宅の立地と大きさを考慮した住宅選択は、都市圏通勤者の睡眠健康の向上につながる可能性があることを示唆している。 本研究成果は、8月29日に国際学術誌「Journal of Transport & Health」にオンライン公開された。
ストレスや疾患などが原因で、一般成人の30%~40%が何らかの不眠症状を有するといわれている。なかでも日本人の1日の平均睡眠時間は、経済協力開発機構(OECD)による2021年の発表では、加盟国33か国中で最も短く、平均を1時間以上も下回っている。
睡眠時間が6時間未満の日本の有職者が適正な睡眠(7時間~9時間)をとれば、1380億ドル(約20兆円)の経済損失を防ぐとの調査結果も報告されている。公衆衛生分野の研究では、睡眠健康を低下させる因子として、長い通勤時間や、都心の過密な居住環境による騒音光害が特定されている。
都心は通勤に便利だが、居住環境に恵まれた住居は郊外に比べて見つけにくい傾向がある。「どのような場所に、どの程度の規模の家を持てば睡眠に良いか」という現実的な問いに答えるには、住宅の立地や規模と睡眠 健康の関係を捉える都市建築分野の研究が重要となっていた。
この研究ではこうした現状を踏まえて、東京都区部に通勤する首都圏在住者を対象に、通勤時間と住宅面積が不眠症や日中の眠気を予測するかどうか、これらの関係が人口統計的、社会経済的因子で調整しても維持されるかどうかを調べたもの。