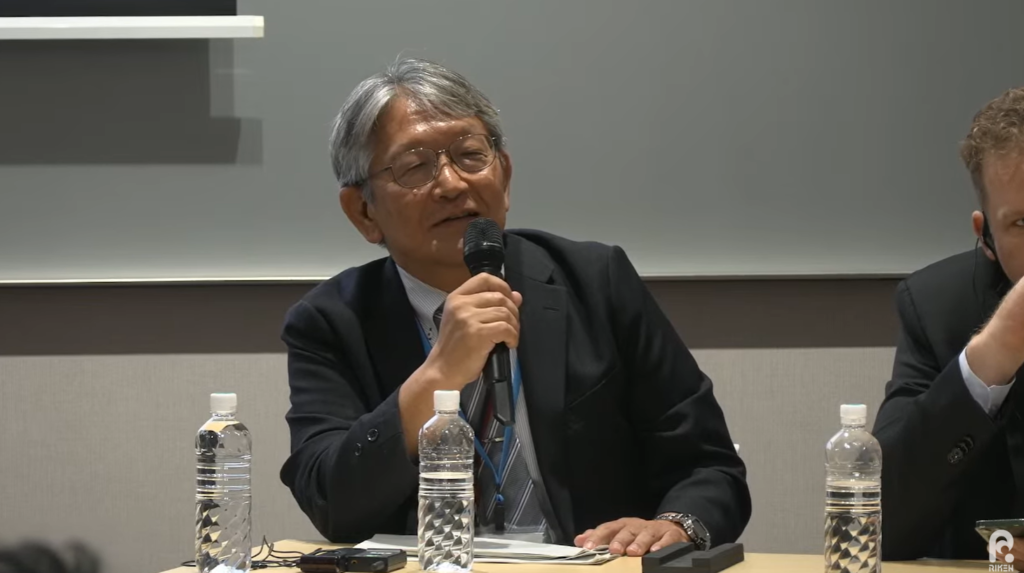理研の佐藤三久・量子HPCプラットフォーム部門長
理化学研究所と日本IBMは24日、同社の最先端量子コンピューター「IBM クオンタム・システム・ツー」(ibm_kobe)を計算科学研究センター(兵庫県)に設置し、運用を開始した。同じ建物にあるスーパーコンピューター「富岳」と結合して、量子・HPC連携プラットフォームを構築して運用する。
量子コンピューターはこれまでの古典的コンピューターと異なる原理で動作する。効率的なシミュレーションや素因数分解などの様々な問題を高速で解けると期待される。両者は今後、新たにソフトウェアを開発して、量子・スパコン連携プラットフォームを構築する。
ibm_kobeと富岳を連携させることによって、従来のスーパーコンピューターで可能な計算が量子コンピューターでもできるようになった。今後、量子コンピューターの優位性を生かしたアプリケーションが開発される見込み。アプリは計算や量子、化学研究などにおいて需要があるという。
理化学研究所の佐藤三久・量子HPCプラットフォーム部門長は「量子コンピューターはこれまで100年かかった計算を1分でできる」とコメント。「今回スーパーコンピューターと組み合わせることで、量子コンピューターでも従来スパコンでしていた計算ができるようになることが大きな成果だ」と評価している。
■HPC(High Performance Computing)
多数のマイクロプロセッサ(CPU)を用いて膨大な演算処理を高速で行えるコンピューターを指す。理化学研究所と富士通が開発した富岳や開発中のスーパーコンピューター「富岳NEXT」もHPCに含まれる。